
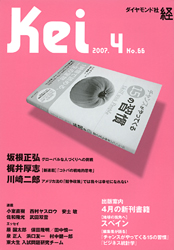
Kei2007年4月号
CONTENTS
エッセイ
- 坂根正弘 グローバルな人づくりへの挑戦
- 浜口友一 同じ戦略、同じITを使っていても、なぜ結果に差が出るのか
- 原 国太郎 日本版SOXであなたの仕事はどう変わるのか?
- 川崎二郎 アメリカ流の「競争政策」では我々は幸せになれない
- 保田隆明/田中慎一 日本企業は株式市場から評価されているでしょうか?
- 泉 正人 お金持ちになりたかったら、お金の知性を磨きましょう!
- 編集者が語る 『ビジネス統計学』(上・下)
- 編集者が語る 『チャンスがやってくる15の習慣』
- 村中健一郎 ストック・オプション会計ですぐに使える計算ソフト
- 東大生 入試問題研究チーム 東大入試問題は日本で一番面白い「脳トレ」だ
- 浜口友一 同じ戦略、同じITを使っていても、なぜ結果に差が出るのか
連 載
◎――――巻頭エッセイ
グローバルな人づくりへの挑戦
坂根正弘
Sakane Masahiro
コマツ(株式会社 小松製作所)代表取締役社長兼CEO。1941年生まれ、大阪市立大学工学部卒業。2001年社長に就任。
建設機械の国内最大手である当社は、売上比率の七割が海外というグローバル企業でもある。
その全世界の社員、約三万五千人に向け新たな取り組みを始めた。そのひとつが企業理念や「グローバルに守り続けたいもの、人が変わっても受け継いでいく信念やノウハウ」をまとめた「コマツウェイ」である。
グローバルな人材教育を考える際、まず普遍的な価値観を社員全員で共有する必要がある。コマツにとっての共通の価値観とは何か、を整理したものがコマツウェイだ。これには、社員全員が持つべき企業理念に加え、開発や経理といった部門ごとに守り続けるべきコマツウェイも記してある。
ものづくりに関するノウハウや品質管理を教えるにしても、手法だけを教育するのではなく、コマツの品質管理の背景となっている考え方や価値観も含めて理解してもらう。そうすることで国や文化の垣根を超えて世界中にコマツウェイが根付き、人が育っていくと考えている。時間はかかると思うが、着実におこなっていきたい。
人材育成については、古くから積極的に教育の場を提供・支援してきた。現在は階層別教育に力を注いでいる。
ものづくりの現場では、コマツ工専を今春から復活させる。現場や取引先の従業員の中から毎年二十名を選抜し二年間、フルタイムで学んでもらうというもの。このコマツ工専を卒業した社員が現場のトップとして力を発揮していることもあり、復活させることを決めた。
中堅社員については、ビジネスリーダー研修という社内ビジネススクールを設置、毎年五十名を選抜して半年間、月に一週間の集中教育をおこなっている。開始してから十年間で五百名がこれを受講し、現在は海外にも対象者を拡げている。ビジネススクールとはいえ理論だけに終わらぬよう、会社経営に役立つテーマでのグループ研究と発表も義務付けている。過去には、研究の一環として中国などへ視察したグループもあった。
海外留学制度も四十年の歴史を持ち、留学者総数は四百名を超えた。こちらは経営に関する知識を得ることに加え、語学や社外のネットワークづくりにも成果をあげていると思う。ほかにも、海外現地法人の次期トップとなりえる人材のコマツ本社での集中教育もおこなっている。
現在、当社の執行役員を兼務している取締役六名は全員が海外駐在経験者である。それだけグローバルなオペレーションを経験した人間が多く、またそこで鍛えられることは大きな財産となっている。
私は「知行合一」という言葉が好きだ。「学問を通じて学んだ知識は、現場でそれを実行にうつしてこそ、はじめて自分自身のものになる」というのが私なりの解釈である。教育し現場で経験させることで人の育成が必然的におこなわれていくのが望ましいかたちだと思う。学ぶ心とチャレンジ精神をもったグローバルレベルで通用する人材が一人でも多く育つよう、いろいろな場を提供し続けていく。
◎――――連載
新連載 コトバの戦略的思考
第1回「よろしくお願いします」
梶井厚志
Kajii Atsushi
1963年生まれ。京都大学経済研究所教授。専攻はミクロ経済学、ゲーム理論。著書に『戦略的思考の技術』『故事成語でわかる経済学のキーワード』等がある
「よろしくお願いします。」
私は九年間海外で生活し、一九九六年に帰国して筑波大学に勤めはじめた。その当時、とても気になったのがこの言葉だ。
海外生活が長かったとはいえ、私は日本で生まれ育った人間だから、初めて会った人と挨拶を交わし、今後とも「よろしくお願いします」とお辞儀をして、にこやかに会話を締めくくることにまったく抵抗はない。にもかかわらず、この言葉が気になって仕方がなかった。そもそものきっかけは、次の依頼文を受け取ったことである。
「梶井助教授殿 留学生からの入学願書を同封しますので、よろしくお願いします。」
それまで日本での就業経験がなかった私は、句読点を除いて二八文字、なんと短歌よりも短いこの簡潔な文章を見て、まずは心から感嘆したものだ。しかし、少々都合の悪いことに、何度くりかえし読んでも意味がわからない。
この場合の「よろしく」という言葉は、生じた問題に程よく適宜対応するという意味であり、したがって「よろしくお願いします」の意味は、作業の実行に際して何か問題が生じた場合は自らの判断を用いて適宜処理することにより、所与の目標を達成すべしということになろう。よって、相手は何らかの作業を私にやらせようという意図をもつということは明らかだ。そこまではいいのだが、いったい何が目標なのかが皆目わからない。そもそも、文書のやり取りをする両者のあいだで目標が暗黙の了解になっている場合にのみ、このような表現が許されるはずではないのか。
仕方がないから書類の送り手に電話をかけて、いったい何をどのようによろしくお願いするのかと尋ねてみると、同封された書類は留学生入学願書であるから、それを読んで評価をせよとのこと。それならばなぜ「同封した留学生からの入学願書を精読して五段階評価をせよ。評価基準については内規X条第Y項を参照せよ。評価が一あるいは五の場合は、一〇〇字以内にまとめた評価理由を添付して、二週間以内に当方まで送り返されたし」などと書かないのであろうか。「よろしくお願いします」からこれだけのことを即座に推察せよといわれても、それは無理な注文というものである。
「よろしくお願いします」に潜む三つの戦略
それでは、「よろしくお願いします」が使われる戦略的理由はいったい何だろうか。これは以下の三点にまとめることができる。
第一は、「よろしくお願いします」という表現に含まれる「協調性」である。冒頭に掲げた入学願書の評価を依頼する文は、たしかに意味がわからない。しかし一方で、私が書きなおした表現ではいかにも一方的な命令調となってしまい、これでは仕事を与える「上に立つ者」と、命令に従い作業をこなす「下で従う者」という上下関係が暗示されてしまう。つまり、これでは上の者の利益のために、下の者が労力を費やし利益を犠牲にするという構造がうきあがってしまうのである。入試の事務作業をする立場の人から、助教授の先生へお願い事をするという場面を考えれば、たしかに先生のほうに細かく指示を出すようなことはしにくいのだろうと容易に想像できる。
誰しも自分の利益に反する行為をすることを面白いとは思わない。だから、上下関係を暗示し利害対立を顕示させるような表現は、戦略的に好ましくないのである。逆に言えば、これからする作業がお互いの利益につながるという、いわゆる『WinWin環境』であると認識してもらえば、仕事は円滑に進みやすい。「よろしくお願いします」という表現を使う背景には、作業を依頼する側が「お願い」する形をとることにより、作業が両者の間での共通の目的であることを相手に認識させる戦略的効果があると考えられるのだ。
第二に、表現に含みを持たせ、あえてあいまいさを残すことで生まれる戦略的効果にも注目したい。表現に含みがあると、その部分をお互いに好都合に解釈できるから、話がまとまりやすくなるのである。
一例をあげよう。事実に反するものではないが、冷静沈着に分析すると内容の乏しい言い回しを、私たちは戦略的に使うものである。相手の服装がセンスのない奇妙なものであっても、それをあからさまに変だと形容するものではない。一方で、とても素敵だから私も真似したい、すぐに一着譲ってほしいなどと思ってもみないことを言ったりすると、かえって具合は悪くなるものだ。それよりは、私ではとても着こなせないなど、どのようにも解釈できる微妙な表現がよい。
職業柄、推薦状や紹介状を書くことがたびたびある。あまりにいい加減なことを書くと自分の評判を損ねるから、思うとおりの所見を少しは書くが、どう書いても最後は前途有望な青年であると結論することにしている。困ったときには将来の可能性を褒めるというのは、この種の状況における一つの定石だ。現状がどうであれ将来には誰にでも何らかの望みはあるものだから、冷静に考えれば前途が有望であるという結論にはほとんど追加的な意味はないが、これもものの言いようというものであろう。
日常生活で、あえて使われる小さなウソは、かえって人間関係を円滑にするという経験則の裏側にも、似たような理由が働いている。物事を克明に描き述べず、あえて含みを残す戦略は、存外各所で使われているものである。
この種の効果を考えれば、「よろしくお願いします」と達成すべき作業に適度に含みを持たせておくと、相手のほうは、場合によっては作業の内容を自分の都合で変えてもよいと解釈し、それが安心感につながり作業に取り掛かりやすくなることもあるだろう。命令された計画どおり寸分たがわず実行するということは結構厄介なものである。
再び依頼文の例に戻ると、私の作文では、するべき作業内容が明確すぎて、かえってやりにくいかもしれない。作業をするのは助教授の先生で、少なくとも建前の上では、願書を評価するという現場の作業は先生のほうがわかっているはずだから、細部を相手に委託してよろしくお願いする態度にも、一理あるといえるだろう。
第三は、理由はともあれ社会的に使われることが標準になってしまうと、標準外の行動をとると損をするという点だ。私たちは右も左もわからぬうちから、よろしくお願いしますという表現を使うことを教え込まれているため、いまさら意味を考えないのだが、これが標準的な言い回しであることは間違いない。
そのような環境で、よろしくお願いする意図をきびしく問いつめたり、妙なコダワリを持ってよろしくお願いすることを怠ったりすると、仕事上でろくなことは起こらないものだ。つまり、言葉に特段の意味はないのだが、標準から外れる損失を回避するために、標準に従う(ロック・インされる)のである。
身近な言葉一つをとって少し考えただけで、これだけの戦略的思考の可能性が潜んでいる。この連載では、身近な言葉や格言・昔話などに取材して、そこに潜む経済学的なアイディアや戦略的な含意を掘り下げて書いてみたい。読者の皆さんよろしくお願いします。
◎――――エッセイ
同じ戦略、同じITを使っていても、なぜ結果に差が出るのか
浜口友一
Hamaguchi Tomokazu
NTTデータ代表取締役社長。京都大学工学部電気工学科卒業後、日本電信電話公社に入社。商用タイムシェアリング・サービスの開発を皮切りに、システム・エンジニア、プロジェクトマネージャーとしてシステム開発に従事。NTTデータ通信(現NTTデータ)に移り、第一産業システム事業部長、経営企画部長、公共システム事業本部長、技術開発本部長、副社長などの要職を歴任した。
変革こそ、経営者本来の仕事
企業の長期的な継続は経営者の使命ともいうべきものですが、経営環境は常に変化し続けています。エネルギー問題、人口減少と高齢化、グローバル化する市場、中国やインドなど新興国の台頭……、私のいるIT業界で言えば、目まぐるしい技術進化、それに伴う従来技術の急激な陳腐化などが挙げられます。
こうした環境下で、私たち経営者は、変えるべきでないものと変えていくべきものをきちんと見きわめ、来るべき変化に立ち向かえるよう企業を変えていく必要があるのです。そしてこの変革こそ、経営者本来の仕事であると言って差し支えないと思います。
ところがいつの場合も変革は容易でなく、しかも変革が根づくまでにかかる時間は期待に反して常に長いものです。大企業の経営者に与えられた時間を考えれば、トライ・アンド・エラーを繰り返して経験値を上げる機会は概して少ないのです。
そのためか、変革のためにさまざまな経営コンセプトがつぎつぎと考え出され、実行されていますが、思ったほどの効果が上がらなかったりすることも少なくありません。
企業に変革をもたらすITを提供する仕事に携わってきた私は、ずっと「どうすればうまくいくのか」を考え続けてきました。そして、うまくいかないのは、コンセプトの妥当性もさることながら、その実行のされかたにあるのではないか、その実行のなかに重要な要素を見逃していないか、ということに思い至ったのです。
重要な戦略も、ある種の道具にすぎない
「M&A」「選択と集中」といった経営コンセプトも、「事業戦略」「財務戦略」「IT戦略」といった重要な戦略も、実のところある種の道具にすぎないのではないでしょうか。
だから、同じ道具を使ってもうまくいくところがあればそうでないところもあるのです。私の腹に落ちたのは、そういうことでした。
この道具たちはとても精緻華麗に構築されているものなので、この強力な武器があれば大丈夫と思ってしまいがちですが、それは大きな誤解なのです。常に変革が要求される企業にとって、経営コンセプトも戦略も大切なものであることは間違いありませんが、道具だけでは企業は動きませんし、変化していくこともできないのです。
では、そういう変革の道具を的確に動かすには何が必要なのでしょう。道具を正しく使うにはヒトの存在が欠かせません。つまり、ヒトのモチベーションが最も重要な要素なのです。
同じ戦略、同じ数字、同じITを道具として使っていても業績に差が出るのは、結局のところヒトの部分なのです。
社員力とは、将来に向かう成長力
私の思い至った変革のドライバー、その諸要件を考えてみると、たとえば次のようなことがあると思います。
●個人の能力が十分に発揮される環境がある。
●個人や組織の学習意欲がある。
●自律的に、創造的に社員が働ける。
●変化することを恐れない。
●関係者のコミュニケーションが円滑。
これ以外にもさまざまな要素が考えられるでしょうが、これらを総合した組織の力を私は「社員力」と呼んでみたいと思っています。
企業は、みんなが同じ価値観を持てばいいというものではありません。社員に共有される同じ価値観は二割もあればいい、残りの八割は異なる価値観であっていい、と私は考えています。いろいろな考え方の人がいる、そのことのほうが大事だと思います。その多様性を認めることで、既存のシステムを破壊することを恐れない雰囲気をつくる。そしてそこから生まれたアイデアを社員で共有し、経営者が方向づけをしていくプロセスが変革を成し遂げるためには不可欠でしょう。これも社員力、と言えると思います。
こうした社員力がなければ、戦略やITは機能せず、変革は成功しないのではないか、というのが私の経験から導かれた考えです。
社員力とは、こうしてみると企業が将来に向かう成長力にほかならないと思います。

『社員力――ITに何が足りなかったか』
浜口友一:著、鈴木貴博:編
●1575円(税込)
◎――――連載
【連載】第10回
最新 MBA用語事典
グロービス経営大学院
嶋田 毅/加藤小也香
Shimada Tsuyoshi/Kato Sayaka
【グロービス経営大学院】
民間のマネジメント教育機関であるグロービス・マネジメント・スクールを母体に2006年4月より発足した経営大学院。「創造と変革」を担う人材の輩出を目指している。
サービス・マーケティング
service marketing
【カテゴリー】マーケティング
サービス業や製品の付随機能としてのサービスに関するマーケティングでは、通常の有形製品と異なるサービスならではの特性―形がない(無形性:intangibility)、生産と消費が同時に発生する(同時性あるいは不可分性:simultaneity, inseparatability)、品質を標準化することが難しい(異質性:heterogeneity)、保存ができない(消滅性:perishability)等――を踏まえてマーケティングを展開する必要がある。
たとえば、ヘアサロンのセットという技術提供には形がないし(無形性)、店側がサービスを提供(サービスの生産)するのと顧客がヘアセットしてもらう(サービスを消費すること)のは同時であり、やり直しはできない(不可分性)。顧客ごとにセットの要望は異なり、また美容師の腕前や接客技術を標準化することは難しい(異質性)。そして、顧客の来店がなければ、美容師がサービスを前もってつくり保管しておくということはできない(消滅性)。
たとえば、いわゆる「カリスマ美容師」を売り出すというやり方は、一見、店の知名度向上につながる良いアイデアのように思える。しかし、前記の要素を理解しないままこれを実行すると、逆に稼働率の偏りを招いたり、顧客の期待値を過度に高める結果、全体としての顧客満足度を下げてしまうなどの事態にもつながりかねない。
一般に、サービス業では、レストランの予約係や接客係、ソムリエのような、企業と顧客の間の接客要員がマーケティング上の重要な要素となる。それゆえ、顧客満足の向上のためには、従来の顧客向けのマーケティングに注力するだけでなく、インターナル・マーケティングによって顧客との接点である接客要員の満足度を向上させることが重要とされる。
[関連語]顧客満足度、従業員満足度
サービス・マーケティング・ミックス
service marketing mix
【カテゴリー】マーケティング
通常、マーケティング・ミックスの4Pといえば、製品(product)、価格(price)、プロモーション(promotion)、流通(place)を指す。しかし、この4Pだけではサービス・マーケティングを包括的に捉え適切な施策を講じることは難しいとして、前記のミックスに新たに参加者(participants)、物的な環境(physical evidence)、サービスの組み立てのプロセス(process of service assembly)の3つのPを加えた7Pでサービス・マーケティングの戦略を組み立てる場合がある。
たとえば、高級レストランではそこで出される料理だけでなく、他の顧客(参加者)や店の雰囲気(物的な環境)、予約時や来店から着席までの応対、料理やワインを選んだりするプロセス(サービスの組み立てのプロセス)によっても顧客満足が大きく左右される。
なお、サービス・マーケティング・ミックスは、通常の4Pほど確立したものではなく、いくつかのバリエーションがある。あるバリエーションでは、新たな3つのPのうち、参加者(participants)を人(people)としている。これは、参加者だけではなく、接客要員なども含め人的要素の重要性を強調するものといえよう。また別のバリエーションでは、新たな3つのPを、人(people)、プロセス(process)、顧客満足への準備(provision for customer satisfaction)とする場合もある。
いずれも、どれが絶対的に正しいというわけではないので、使いやすいものを使えば十分である。ポイントは、人やプロセスを軸に、通常の商品マーケティングではあまり現れてこない要素が重要である点を理解することである。
[関連語]マーケティング・ミックス、サービス・マーケティング
内部顧客
internal customer
【カテゴリー】経営戦略、オペレーション・マネジメント
社内で次の工程を引き継ぐ担当者、組織のことを内部顧客という。一般の顧客を外部顧客と呼ぶのに対し、川下の従業員を内部の顧客とみなす考え方であり、内部顧客を満足させることは、外部顧客の満足につながるという考え方である。
企業によっては、川下の組織である内部顧客に、外部からの調達を許可しているところもある。こうした企業では、内部顧客を満足させられない場合、売り先を失ってしまうことになる。そうならないように、内部顧客の要望に耳を傾け、その満足度を高める施策をとるようになることが期待される。
なお、こうした施策を導入している企業では、川上の組織に外部への販売も許している場合が多い。上工程と下工程のそれぞれを担う組織を独立企業のように扱うことで、外部環境への意識を高めるとともに、当事者意識や採算マインドの向上を期待しているのである。
[関連語]バリューチェーン、外部顧客
![[新版]MBAマーケティング](50247-1.jpg)
好評発売中!MBAシリーズ
『[新版]MBAマーケティング』
●2940円(税5%)
◎――――連載
第4回 ロックの思想とキリスト教
小室直樹
Komuro Naoki
1932年生まれ。京大理学部卒、阪大、東大院修了。ハーバード大、MIT、ミシガン大各大学院へ留学。
著書に『危機の構造』『経済学をめぐる巨匠たち』など多数ある。
マルキシズムに優るロックの思想
ロックの思想は、燎原の火の如く、全ヨーロッパに広がっていった。昔の人ならば、マルキシズムの如くと表現したであろう。
しかし、マルキシズムは、ソ連の崩壊によって消え去ったのに対し、ロックの思想はというと、それを先駆けとして生まれた資本主義が未だに隆々として栄えている。故に、ロックの思想は、マルキシズムより遙かに強かったとさえいえる。
フランスでは、ナポレオン法典の根幹を今もそのまま維持しているではないか。例えば、私有財産の絶対、事情変更の原則の拒否など。これだけを見ても、ロックの思想がマルキシズムよりも遙かに根強く、遙かに根本的であることがわかるだろう。
例えば、アメリカの政治の思想といえば、直ちにロックの思想を意味する。
ロックを源にアメリカ帝国が出現
ケインズは“セイの法則”を拘束したが、セイの法則を成立させるためには、私有財産の絶対が必要であり、やはりロックの思想の上に立っている。
シャハト(一八七七〜一九七〇年)が、ヒトラーの経済大臣として、インフレなき好況を実現し、わずか六年の後、一〇万の陸軍からヨーロッパ最強の大陸軍を作り上げたということは、資本主義の本質を見極めているという意味で、やはり、ロックの真髄を見ているというべきであろう。
このように、ロックの思想は、スミス、リカードからケインズに至る諸学者だけでなく、ヒトラーからイスラム原理主義者に至るまで影響を与え、宗教家もまたその本質に引き寄せられたのであった。
ロックの思想を根本として、アメリカは、中国の秦の帝国の如く、あるいはローマ帝国の如く、今やアメリカ帝国となり、パクスアメリカーナを実現している。これまたロックの思想の出現か。
このアメリカがいつ滅びるかについても、秦やローマ帝国を参考にすべきである。
なぜロックの思想が体現できたのか
ロックの思想は、アメリカでこそ実現した。それは、アメリカの独立宣言に表れただけではない。いとも奇妙なる宗教「キリスト教」がアメリカに渡って初めて、その本来の姿を現して大活躍を始めるのである。
ここでもう一度、キリスト教について振り返ってみよう。
キリスト教の本質とは、「予定説(ルビ=プリディスティネーション)」であり、啓典宗教(ルビ=リビールド・レリジョン)である。プリディスティネーションやファンダメンタリズム(奇跡を事実だと信じている者)といったものは、アメリカにおいて初めて顕示的(ルビ=リビールド)に現れる。
アメリカの建国の時には、アメリカ合衆国の理想は何一つ実現されていなかった。自由主義も、資本主義もなかった。民主主義に至っては、一断片すら見当たらなかった。あるのはそれを目指して進むという決意だけであった。
それが、時が経つに従って、一つ一つ実現されていく。これこそ、まさに神の意思そのものではないか。「ヨブ記」の論理の徹底ではないか。
また、アメリカの時代になって初めて聖書が普及したことも注目に値する。ヨーロッパにおいては、聖書を読むと焼き殺される宗派さえあったのである。
アメリカでのキリスト教の実態
アメリカの時代になってから、キリスト教には余りにも見るべきものが多かった。例えば、今や『グッド・ニュース・バイブル』となっているものがある。本来、福音(evangelium)と訳すところを「グッド・ニュース」と訳した。赤ん坊や子供でも聖書がわかるようにするという趣旨で訳された聖書である。
「我が言を聞きしや」とするところを「グッド・ニュース」とした。これくらいわかりやすく聖書を訳すのだが、なんとアメリカ聖書協会の宿老までもがこの訳に参与しているのである。昔は、聖書のラテン語訳ですら、教皇の秘書を務めた聖書学者ヒエロニムス(三四二頃〜四二〇年)によって初めて翻訳されたくらいであった。何という違いであろうか。
これすべてアメリカの所産である。
予定説の論理が一般人の間にも普及し、宗教家だけでなく、発明家、実業家などの間にも多く見られることは、既に述べた(第1回参照)。
ファンダメンタリズムは二一世紀になってもまだ残っている。聖書の内容を絶対視することから、進化論を否定する裁判、つまりモンキー・トライアルもしばしばなされている。
それどころか、予定説を外国にも広めようとし、しばしば戦争まで起こしているではないか(古くは、我が国にペリーが開国を迫ってきて、開国しないなら戦争するという脅し、日本への不平等条約、最近では、湾岸戦争やイラク戦争など。その他、アメリカのする戦争)。
キリスト教の邪教・邪説
中世のキリスト教は、一神教としては珍しく、邪教・邪説が多かった。教会から離れたところに住む人々に多いだけでなく、教会そのものも邪教・邪説に満ち満ちていた。
例えば、洗礼に使った水は病気にも効くとか、終油の油は難病の特効薬だとか、神父が上った教壇に上ると“てんかん”が治るとか……etc。
中世中期までのカトリックにおける因習は、「疑わしきは罰する」ということであった。故に「疑い」つまり「嫌疑」をかけられると、拷問をかけられるので、これに耐えることが当時の能力の一つであった。
かの有名なサボナローラ(一四五二〜一四九八年、イタリア人ドミニコ会の修道士。宗教改革の先駆けとなる)も「雄弁広辞あたる所なき」能力を有しながらも、拷問に耐える力が弱かったというだけで、有罪となり、死刑になってしまった。
だから、この時代の人々の間の論争も、結局は拷問に耐えるだけの競い合いであった。
それ故に、キリスト教の論理は僧侶の間においてすら徹底することはなく、邪教・邪説は、宗教改革が起きるまで、至る所にはびこっていた。
宗教改革のテーマは、このような邪教・邪説の論理を、キリスト教本来の論理で、打破することであった。
中世の教会は、疑いを発することは自由で、「疑わしきは罰せず」ではなく、疑われることは有罪だから、魔女・魔人(ルビ=ディセンダー)だと嫌疑をかけられる人々を、実質的に支配する権限を持っていた。こうした人々は、至る所に幾らでもいたから、この意味で教会の勢力、権限は絶大になっていった。
教会の勢力は、無限に拡大する方向を有していた。魔女・魔人(ルビ=ディセンダー)だけではなく、カトリック教会のディセンダーたちは、人々の倫理的評価を与えたから、この意味においても、中世社会を襲断していたともいえる。
このように、キリスト教の原理とはまったく無関係な、単なる人々の気持ちによる任意評価が社会一般を覆いつくしていたといえる。
極端な判例としては、“背徳の町”とか“悪魔の村”とか、そういうものさえ存在した。この町や村に行くと、“福音書はすべて逆に読め、バイブルなんてめっそうもない”というルールが支配した。こうした人々は、朝から晩まで、正気の沙汰には見えないが、本気でこのようなことを実行していたのである。
宗教改革によって、ルター(一四八三〜一五四六年)やカルヴァン(一五〇九〜一五六四年)が出てきた時、この逆の村や町を如何に処理すべきかに、かなりの苦労をしたのである。
これらのことは、魔女裁判が中世末期、資本主義勃興の直前に行われたことを見ても証明されうるであろう。
奇天烈な中世のキリスト教
実際、魔女の嫌疑をかけられた者は、古代、中世初期、中世中期にも至る所にいたが、魔女裁判が中世末期に集中したのは不思議とは思わないか。その理由は、キリスト教は一〇〇〇年以上も前に、ヨーロッパに入ってきたと伝えられるが、当時のキリスト教は一神教としては真に奇妙奇天烈であったからである。
キリスト教の根本的教義の一つは、三位一体説(トリニティ)なのだが、子なるキリスト、天にまします父なる神、聖霊(ホリーゴースト)、という聖なる三位を認めれば、三神教にならないか。それに、聖母マリアを加えれば、四神教にならないか。
だから、イスラム教およびイスラエルの宗教(バビロン捕囚の後にユダヤ教となる)に比べれば、キリスト教は一神教とは認めがたい。モーゼは三位一体説のような戯言を一言も言っていない。モーゼの母はエジプトの王女であっても、神であるなどとは言っていない。
イスラム教に至っては、ムハンマドの母について、一言も触れられていない。
だからイスラム教やユダヤ教から観れば、キリスト教の三位一体説や聖母マリアなど、とんでもないことなのだ。
キリスト教が本来の姿に戻ったのは、実をいえば、宗教改革まで待たなければならなかった。つまり、ルター、カルヴァンの出現を待たなければならなかった。
それまでに改革をなさんとする者が出てきても、キリスト教からの迫害を受けて、焼き殺されるのが常であった。教会でも聖書は読ませられず、聖書を読んだ者は焼き殺された。信者が読んだものといえば、祈祷書を読ませられ、賛美歌を歌うだけであった。
このように、宗教改革前のキリスト教はひどいものであり、宗教改革後、特にアメリカに渡ってから、キリスト教は本来の姿を取り戻したのである。
◎――――エッセイ
日本版SOXであなたの仕事はどう変わるのか?
原 国太郎
Hara Kunitaro
米国公認会計士、公認情報システム監査人、公認内部監査人。監査法人トーマツ エンタープライズ・リスク・サービス勤務。京都大学経済学部卒。大手ビジネスコンサルティング会社にて石油、電子機器、半導体企業等のサプライチェーン構築・ERP導入プロジェクトに参画後、監査法人トーマツに入所。大手商社の業務再構築プロジェクトにおける内部統制コンサルティングを経て、米国企業改革法(SOX法)適用初年度の2004年には計10社の外資系企業について、SOX法対応を支援又は内部統制を監査。2005年より自動車メーカーの内部統制報告書制度(日本版SOX)対応プロジェクトにトーマツチームのリーダーとして参画。
内部統制とは何か
「日本版SOX(金融商品取引法に基づく内部統制評価報告制度)の実施基準が最終化され、上場企業約3800社がいよいよこの新たな制度への対応を迫られることになりました」
こう聞くと、「なんだかまったく新しい仕組みが導入され、自分たちの仕事がいろいろ変わってしまうのでは……」と思う方もいらっしゃるかもしれません。それはたしかにそうでもあり、しかし、意外とそうでもないのです。
内部統制とは何でしょうか?
思いきってひと言でいうなら、「会社の管理がしっかりしているかどうか」でしょう。一般に「管理」というと、伝票を記入したり承認を得るための手続だったり、またそれに時間がかかったりと効率性に反するようなイメージがあるかもしれません。
しかし、管理がまったくない業務というものをちょっと想像してみてください。もし経費の請求に対して承認がなかったら、経費がムダに使われてしまうこともあるでしょう。もし新規の取引先をまったく調査もせずに商品を販売すれば、代金の回収ができないこともあるに違いありません。バランスのとれた「管理」または「内部統制」は、間違いなく業務の効率性に貢献するものです。
したがって日本版SOXを簡単にまとめるなら、「あなたの会社、あなたの部署、あなた自身が『日々の業務をしっかり管理できている』ことを改めて示すように求めているだけだ」ということになります。
では、自分の会社の業務がうまくいっている自信があれば(課題や問題は尽きないでしょうが、もちろんうまくいっている方がほとんどだと思います)、何もせずに安心していられるのかというと、そういうわけにもいきません。内部統制の導入によって、変わらなければならない点が、少なからずあるからです。
第一に、「しっかり管理できている」ことを、第三者が納得できるように客観的に示すのがなかなか大変です。例えば、管理者が「自分は部下の実施している業務は把握できている」と思っていても、文書等で残されていない部分は第三者には見えないからです。
第二に、改めて「内部統制」と呼ばれるだけのことはあって、実務的に求められる内容に、これまでの日本企業ではあまり行われていなかった新たなものがいろいろと含まれていることです。
内部統制導入の勘所
米国SOX法は、その対応の費用や工数が企業への大きな負担になったとして議論を呼びました。日本版SOXには、企業の負荷を軽減するような工夫がなされていますが、それでも相応の工数・費用がかかることが想定されています。
制度の目的は、財務諸表の信頼性を確保する(または信頼を回復する)ことですから、財務報告に係る内部統制に「重要な欠陥」さえなければよい、という考え方もあります。たしかに、財務報告に重要な影響を及ぼす内部統制に着目することは非常に重要です。しかし、金額的重要性の面からいうと、巨額の利益をあげている会社、実施基準の例示に沿っていえば、連結税引前利益が一〇〇〇億円あるような会社であれば、その五%の五〇億円に影響を与える可能性のあるような内部統制上の不備のみが重要な欠陥になりえます。
そのような大きな問題点は、それこそ決算・財務報告プロセスや、売上計上基準、繰延税金資産といった、よく会計処理上の問題となるようなところからしか、ほとんど出てこないかもしれません。しかし、それでは数千万円の不正・誤謬の可能性はどうでもよいのか、というと決してそうではありません。
第一に、企業が常に巨額の利益をあげ続けられるとは限らず、むしろ継続企業の前提から「山あり谷あり」だと考えるべきです。大きな利益をあげている時には十分な内部統制だが、利益が出なくなれば不十分というのでは、適切に整備されているとはいえません。
第二に、「塵も積もれば山となる」で、同じ勘定科目に対して影響を与える内部統制上の不備はすべて加味して考えることが適切な場合もあります。理論上は数千万円の影響を与える同じような不備がたくさんの事業部・子会社にある場合には、重要な欠陥になりえます。
第三に、子会社を個別に上場したり、事業部を他社に売却する場合もあるでしょう。個々の子会社・事業部として見た場合に、あまりに粗い内部統制の構築・評価では、かわいい子にも旅をさせられません。
第四に、一般に財務報告に係る内部統制と考えられる領域について手を抜いた場合、言い換えると、他社よりも相当程度に粗い構築・評価をした場合には、実際に何か問題が起こった場合、株主代表訴訟といったリスクもありえないとはいい切れません。また外部監査人はどうしても残高に引きずられる傾向があるので、結果悪ければすべて悪しということで、評価範囲に入らなかったところに決算上の誤りが生じた場合、内部統制上の問題点だと指摘してくる可能性が大いにあります。
「最低限の対応しかしません」はよろしくない
というわけで、時々「最低限の対応しかしません」というスタンスの会社またはご担当を見かけますが、これはよろしくありません。他の法令やリスクについて、例えば、「製品の安全性は消費者に訴えられないギリギリでよい」「製造工程の環境対策は法令に違反しないギリギリでよい」といった考え方はされないと思います。なんでもそうですが、適度のゆとりを配して対応することが適切です。
日本版SOXを機に、一般に求められると考えられる財務報告に係る内部統制についてきちんと点検し、問題点をよく吟味したうえで、たとえ制度上必要とは限らないものでも、会社の管理として当然行われているべきもので、かつ費用も大きなものでなければ、改善を進めて身ぎれいにすることが適切だといえるでしょう。

『内部統制で現場の仕事はこう変わる』
原国太郎/矢野直:著
●1680円(税5%)
◎――――エッセイ
アメリカ流の「競争政策」では我々は幸せになれない
川崎二郎
Kawasaki Jiro
衆議院議員。前厚生労働大臣。一九七一年、慶應義塾大学商学部卒業、松下電器産業株式会社に入社。一九八〇年に第三六回衆議院選挙に初当選。二〇〇五年一〇月、第三次小泉内閣で厚生労働大臣に就任。医療制度改革をはじめてする数多くの重要課題で多くの功績を残す。一九四七年生まれの「団塊の世代」の政治家として、積極的な発言をしている。
人口減少が加速する日本
二〇〇六年一二月二○日、厚生労働省の国立社会保障・人口問題研究所が、わが国の長期的な人口動向を予測した「将来人口推計」を発表した。〇二年一月の前回推計から五年ぶりの改定だ。
それによると、移民などによる人口の大規模な流入がないとすれば、二〇五〇年にはわが国の人口は九五一五万人。五五年には八九九三万人になると予測されている。現在の一億二八〇〇万人から実に三割も減少、全人口に占める六五歳以上の人口の割合を占める高齢化率は四〇・五%となり、現在のほぼ二倍に跳ね上がるという。
一人の女性が生涯に産む子どもの推定数を示す合計特殊出生率は、二〇五五年に一・二六。〇五年と同程度だが、前回推計の一・三九からすると大幅に下方修正された。
国民経済の面では、少子化や人口が減少するということはきわめて重要な問題である。経済の潜在成長力が人口動態と生産性に規定されることを考えると、経済が停滞し、国民は経済的に恵まれたかたちでの豊かな生活が望めなくなる。人口が急激に減る段階では、それどころか貧しくなってしまう可能性が高い。
また、年金や医療、介護などの社会保障制度の面では、支える人口が減ることは制度の根幹を揺るがしかねない。少子化や人口減少という問題は、国民全体で真剣に対策を考えていかなければならない時期にきていることは間違いない。
競争政策はバブル崩壊後に始まった
バブル崩壊後、なんとか経済に活力を取り戻すべく、政府は規制緩和、減税、公共投資などの対策を矢継ぎ早に打ってきた。しかし、それでもほぼ一〇年を超える長い期間、わが国の経済は停滞を続けてきた。
現在、企業は空前の利益を上げ、景気は長い拡大を続けているといわれているが、これは政策の帰結というよりも、リストラや中国への輸出の急増で活力を取り戻したと見たほうが正しい。政府の大胆な経済政策にもかかわらず、働く国民の賃金は上がらず、個人消費も伸び悩んでいる。個人消費を中心にした内需をたしかに回復させなければ、景気は早晩腰折れしてしまう可能性が高い。
政府が採用してきた政策は、いわゆるアメリカ流の「競争政策」と言われるもので、規制緩和によって企業の自由度を上げ、事業活動を展開しやすくすることが基本にはある。こうして企業の競争力が高まっていけば、国民経済が活性化し、その恩恵が従業員や国民に波及していくという発想なのだ。
経済が成長してその恩恵を従業員や国民が享受する。それがうまくいけばもちろん言うことはない。しかし、アメリカにならって競争政策を一〇年以上も採用してきた結果はどうだったのか。
少子化、人口減少の背景とは
正社員は慢性的な長時間労働を強いられ、若い人を中心に一六〇〇万人余りが派遣社員やパートといった不安定な身分で低賃金を競うような叩き合いの社会をもたらした。結果的には、若い人が安心して子育てもできないような社会にしてしまったのではないか。いつの間にかそういう社会になってしまっていることに目を向けなければならない。
子どもを産むかどうかは、究極的には個人の選択の問題であり、そもそも国や社会や他人が強制できるような問題ではない。しかし、世の中には「子どもが欲しくても子どもが持てない」という若い人たちがたくさんいる。
「今の給料では自分が生活するだけで精一杯」「いつリストラされるかわからない」「派遣やアルバイトで生活が不安定」「長時間労働が常態化していて子育ての時間が取れない」など、人生設計が描けず将来に不安のある若い人たちは、子どもが欲しくても子どもを持つ決心ができないという現実があるのだ。
実は、こうした原因、背景があって少子化、人口減少が加速的に進行しているというのが私の見解なのである。
このまま競争政策を強めていいのか?
にもかかわらず、今、政府は経済成長を加速的に進めるために「上げ潮政」なるものを掲げている。これは、さらに規制緩和を進め、企業減税を実施し、企業の競争力を強化しよういうものだ。
政府が掲げる政策は、単に従来のアメリカ流の競争政策の方向性を強めただけであり、バブル崩壊後の経済が長期的に低迷したことなどを併せて考えると、今後の政策の方向性として十分なものとは思えない。
もちろん、規制緩和に代表される競争政策すべてが悪いというのではない。そういう政策を一〇年以上継続してきた現在、よくなった面と悪くなった面、利点と弊害とをそれぞれ比較して、検証する時期にきているのではないか。
幸い景気も拡大しているのだから、ここでアメリカ流の「成長優先」「競争政策」の悪い面は思い切って政策的に転換し、同時にそれを支える日本人の働き方や価値観、つまり「長時間労働」を美徳と見なすような、働き過ぎの文化を改めるべきだと私は提言したい。
競争社会すべてを否定するのではないが、強者・勝ち組が敗者・負け組にいたわりの心を持つ社会に戻さなければならないと思う。子どもを持ちたい若い人たちが、子どもを持てるような社会を実現していくことが、結局、経済を活性化するとともに、社会保障制度をも充実したものにしていく近道になるはずだ。

『このまま「アメリカ型」社会を目指して本当に幸せになれるのか?』
川崎二郎:著
●1680円(税5%)
◎――――エッセイ
日本企業は株式市場から評価されているでしょうか?
保田隆明
Houda Takaaki
ワクワク経済研究所代表。リーマン・ブラザーズ証券、UBS証券、SNSサイト運営会社の起業、ネットエイジキャピタル執行役員を経て現職。著書に『投資事業組とは何か』共著、『投資銀行青春白書』(ともにダイヤモンド社)、『なぜ株式投資はもうからないのか』(ソフトバンク新書)など多数。ブログ:http://wkwk.tv/chou
田中慎一
Tanaka Shinichi
株式会社インテグリティ・パートナーズ代表取締役。KPMGセンチュリー監査法人(現・あずさ監査法人)、大和証券SMBC、UBS証券、港陽監査法人を経て現職。著書に『投資事業組合とは何か』共著、『ライブドア監査人の告白』(ともにダイヤモンド社)がある。ブログ:http://d.hatena.ne.jp/ilovefirenze/
コーポレートファイナンスに関する彼我の差に愕然
大学卒業後、外資系投資銀行の東京支店に入社した私は、二〇〇一年の一年間、ニューヨーク本社にてグローバルM&Aグループの一員として働く機会に恵まれました。赴任前はM&A、株主資本主義の先端を行くニューヨークオフィスの同僚や先輩、上司のレベルに自分の知識と経験はついていけるだろうか、と不安に思いました。
幸いなことにM&A理論、財務戦略理論は世界共通なので、苦しみながらも対応できましたが、予想外にショックだったことは、コーポレートファイナンスやM&Aに関する米国のクライアント企業の理解度、そしてクライアントから投資銀行に求められるもののレベルの高さでした。
クライアント企業と一口に言っても、お付き合いをするのは経営者層から事務方の若いビジネスパーソンまでさまざまですが、どの層の方も、M&Aやコーポレートファイナンスに関してある程度の理解があり、私が東京にいた当事クライアントに説明してもなかなか分かってもらえないようなこともすんなりと理解してくれました。むしろ、「これはどういうことだ?」「こういう場合はどうなんだ?」と自社の株価の状況を交えながらいろいろと質問してきます。ミーティングが終わるたびに、私たちはたくさんの宿題を抱えて、また後日クライアントに提案をすることになります。
彼らは、投資家、株式市場からの評価をうまく自社の企業戦略に反映していました。株価が低ければ戦略のどこが評価されていないのか、また、より評価されるにはどのような戦略があるかを日々考え、実行していました。一方、市場、株主に誤解や理解不足があると見るやIRという直接対話によってその解消に努めていました。
ビジネスの世界は、一言で表すならば戦場だと思います。異論もあるでしょうが、「勝った負けた」の世界であり、その結果は数字で如実に現れます。M&Aや財務戦略が今後企業の大きな武器になっていくのであれば、当時の日本企業のその分野に対するリテラシーとアメリカ企業のそれを比べるに、日本企業はビジネスという戦場でボロ負けしてしまうのではないか。「日本ってすごいんだ」と思って育ってきた世代の人間として、それは屈辱的なことでありました。
機能不全に陥った日本企業の活路としてのM&A
著者二人は、団塊ジュニアの世代であり、多感な中学・高校時代を“ジャパンアズナンバーワン(Japan as No.1)”のバブル期にすごしました。自分たちの将来はバラ色だと信じて疑いませんでした。しかし、大学に入学する頃にはバブルが崩壊し始め、待っていたのは就職氷河期とその後に訪れる平成金融不況。大手金融機関から内定をもらっていた同級生が、入社前に会社が経営破たんするという時代です。
誰の目にも明らかに日本経済は機能不全に陥っていました。そして、私たちはともに、日本経済立て直しのためには大手術が必要だと思い、それぞれM&Aというものに出会います。それがお互い投資銀行に入社するきっかけでした。
私たちが投資銀行勤務時に見たのは、日本企業でも現場レベルの若手ビジネスマンは自分たちもM&Aや財務戦略を活用して企業価値を意識した経営をすべきだという考えを持っていたことです。一方、経営会議、取締役会のレベルになると、その理解は残念なレベルでした。
その後、二人ともベンチャーの起業、ベンチャーに対する財務コンサルティングや監査、そしてベンチャーキャピタル業などに従事し、ベンチャー経営者とも数多くつきあうようになります。彼らは確かに危機意識が高く、M&Aや企業財務に関してもよく勉強し、株式市場からの評価に対しても敏感でした。
しかし、同時に株式市場が上げ潮だったこともあり、拝金主義的な考えに陥ってしまったベンチャー経営者が少なくなかったのも事実です。
一方、当時のエスタブリッシュ企業に目を転じますと、村上ファンドやライブドアという急進派の登場により、経営者の方々が大きく動揺している様子が伺えました。みな、企業価値の視点での経営、市場を意識した経営を心がけているようで、発言と行動の整合性が取れていないケースも多々ありました。
M&Aもコーポレートファイナンスも非常に論理的で一つひとつは理路整然としています。これほどロジカルで分かりやすい分野も少ないのではないかと思います。しかし、実際の企業経営では、この突然やってきたM&A、コーポレートファイナンスの時代についていけず、むやみに感情的な言論が飛び出したりしています。
こうした環境変化をふまえて、企業経営者の方々にとって、M&A時代の株式市場との付き合い方はどうすればいいのか、をまとめてみたいと思いました。私たちの投資銀行勤務時代は、悔しいかな日本企業が株式市場からバカにされる日々が続きました。それがやっと最近、M&Aやコーポレートファイナンスに関して、前向きに活用したいという機運が高まってきました。本書が、皆様の理解に少しでもお役に立てれば幸いです。

『M&A時代 企業価値のホントの考え方』
保田隆明/田中慎一:著
●1680円(税5%)
◎――――エッセイ
お金持ちになりたかったら、お金の知性を磨きましょう!
泉 正人
Izumi Masato
日本ファイナンシャルアカデミー株式会社 代表取締役。1974年、横浜市生まれ。中学卒業後、米国の高校(カリフォルニア)に単身留学。留学中に出会った美容師に憧れ、16歳で高校を中退して美容学校へ入学。卒業後、ヘアサロンに勤務するが、美容師としての才能に限界を感じ、23歳でITベンチャーへ就職。27歳でファイナンシャル教育を行う日本ファイナンシャルアカデミー株式会社を設立し、現在に至る。28歳の時に始めた不動産投資では、3年間で15棟の不動産資産を持ち、年間家賃収入2億円を得るまでになる。
預金通帳でわかるお金の知性
「あなたの預金通帳は、お金の履歴書だ」
この言葉を聞いたとき、僕はとても衝撃を受けました。自分の預金通帳には、いつもほとんど残高がないので、恥ずかしくて他人にはとても見せられないと思ったからです。
まさしく、預金通帳はお金の履歴書だといえます。そして、それを見ればその人にお金の知性があるかどうかがわかるといっても過言ではないでしょう。
10年前、僕は渋谷のあるヘアサロンで美容師をしていました。毎月17万円ほどの給料を、ほぼすべて使い尽くしていました。都内の築50年、家賃4万円のアパートに住んでいましたが、クルマを所有し、毎日遊んだり飲んだりしてお金を使っていました。毎月のようにそんな生活をしていたのですから、給料はあっという間になくなってしまうのも当然です。
そればかりか、お金がなくなると、分割払いでサーフボードを買ったり、新しいクルマが欲しくなるとローンで買ったりもしていました。
「給料が少ないから、お金なんて貯めるのは無理だよ」
当時は、こう言って自分を納得させていました。
その後、23歳でITベンチャーに就職。サラリーマンになって年収は400万円くらいになりましたが、収入が増えても、お金が貯まることはありませんでした。かえって収入が増えたことによってローンが組みやすくなり、借金が増えるようになってしまいました。
お金が貯まらない真の原因がわかった!
お金が貯まらなかったのは、収入が少ないという理由だけではありませんでした。あとでわかったのですが、「お金の知性」がなかったことが本当の原因だったのです。
収入―支出=借金生活
毎月のようにこんな状態では、お金が貯まるはずがありません。
あるとき、「こんな生活をしていてはダメだ!」と一念発起し、お金について勉強する決心をしました。
しかし、何から始めたらいいのかまったくわからなかった僕は、片っ端からお金関係の本を読み、毎月、さまざまなセミナーに通い、成功者の話をたくさん聞くようにしました。
スポーツのトレーニングと同じで、お金の知性もトレーニングをすれば身につくものと信じて、これを続けました。
やがて、このトレーニングの効果が現実のものとなっていきました。10年前は貧乏でお金の知性がまったくなかった僕が、「お金の脳トレ」をやり続けたおかげで、いまでは5つの会社を経営し、15棟のビルやマンションを所有し、経済的な自由を得ることができるまでに成長できたのです。
「お金の知性」は格差社会を生き抜くために不可欠の道具
僕がやったことは、特別に難しいことではありません。
働いて得た給与の2割で勉強する(自己投資する)→給与の2割を貯金に回す(種銭づくり)→貯まったお金を元手にして投資を始める→投資から得られた利益の一部を、ふたたび投資に回す→投資から得られた利益の一部でぜいたく品などを買う。
意識して、こういうお金の流れをつくり出したのです。こうしたお金のサイクルをつくることができれば、誰でも自然とお金持ちになれます。
20年前は、「これからは英語を勉強したほうがいい」といわれていました。10年前は、「これからはパソコンができたほうがいい」といわれていました。そしていま、お金について勉強する時代になったのです。
お金の知性は、これからの格差社会を生き抜くために、誰にとっても必要不可欠な道具といえます。本書が、あなたの夢をかなえる力になれば幸いです。

『お金の脳トレ たった4つのステップで、あなたも億万長者になれる!』
泉 正人:著
●1500円(税5%)
◎……編集者が語る
『ビジネス統計学』(上・下)
アミール・D・アクゼル、ジャヤベル・ソウンデルパンディアン:著
鈴木一功監訳、手嶋宣之、原郁、原田喜美枝:訳


上下巻定価各4410円(税5%)
赤リンゴが上巻、青リンゴが下巻
統計学の素養がまったくない編集者が、ビジネスで使える本格的な統計学の書籍の編集を担当してしまいました。
本書の原書Complete Business Statisticsは、欧米のビジネススクールでは定番となっている教科書です。最初の発行は一九八九年で、その後改訂を六回も繰り返してきた定評あるものです。
そもそも統計学は、ビジネススクールではどこでも必修科目です。しかしこれまで多くのMBA本が翻訳されているにも関わらず、いまだ一冊も日本で紹介されなかった領域です。その意味で、本書は「MBA版」統計学の初の翻訳書となります。
本書の特徴は、まずビジネスユースに徹した構成であること。多くの統計の本が、生産管理や人口統計の例などで構成されているのに対し、本書では、ファイナンスやマーケティングの事例が豊富に出てきます。また数式も出てきますが、飽くまでそれらを通して、どのように統計を使うかを重視しています。そのため、読者が本書で学んだことをすぐに実践できるように、数式を埋め込んだエクセルファイルがウェブ上からダウンロードできるようになっています。
特徴のもう一点は、例題、事例の豊富さです。理論や用語の説明の後に、具体的な使われ方の事例や例題が出てくるので、何のためにその知識が必要で、それが理解できたかが分かりやすい構成になっています。
さて、統計学素養ゼロの編集者は、編集過程で原稿を四回読みました。最初に読み始めたとき、平均値や中央値の使い分けなど、まさに合点のいく説明に深く頷きました。しかし、それも2章までで3章で「??」になってしまいました。二度目に読んだ際には、3章を突破できたのですが、6章で新たな壁にぶつかりました。「信頼区間」という章です。監訳者に伺うと、多くの学生がこのあたりで挫折してしまうそうです。新たに挑んだ三度目、じっくり読み進め、見事に6章の壁を乗り越え、一気に10章まで快適に読むことができました。そして四度目で、残り3章も突破でき本書全体を理解することができました。本書を通じて、ビジネスの状況をこれほど数字で表現できることに感動すら覚えました。
素養ゼロの編集者がこれですから、統計学に縁のある読者なら、独学でも本書で相当の知識が身につくのではないでしょうか。普段、統計学を使いこなしておられる読者も、新たな気づきが得られる本だと思います。
(編集担当 岩佐文夫)
◎……編集者が語る
『チャンスがやってくる15の習慣』
レス・ギブリン:著 渋井真帆:訳

定価1260円(税5%)
チャンスは人が運んでくる
発売後、1カ月で5万部に達した話題のベストセラー『チャンスがやってくる15の習慣』。
本書は、アメリカで企業研修の教材として500万部以上売れているコミュニケーションの教科書です。
この本の翻訳を出版することになったきっかけは、本を出すたびにヒットになる、カリスマ・キャリアアドバイザーの渋井真帆さんが、
「どうしてもこの本を翻訳したい」
と、企画を持ち込んできたことからでした。
そのとき、なぜ彼女がこの本を翻訳したいのか、その理由を聞いて、私は、人生について、何かたいへん大きな納得をしたのを覚えています。
そして、その話は絶対に前書きに書くしかない、ということになりました。(だから、前書きは、必ず読んでみてください)
*
人が成功するには、何か方程式のようなものがあります。
私は、それが何なのかは、うすうす感づいてはいましたが、その時の、彼女の話を聞いて、そして、この本の原書を読んで、成功するためのイメージが、かなりはっきりしました。
私は、編集者として、たくさんのビジネス書ベストセラー作家と親交がありますから、成功の匂いに非常に敏感です。
*
現代のビジネス書ベストセラー作家のほとんどは、自分でも何かビジネスを持っていて、本だけでなく、ビジネスパーソンとしても成功者です。
そんな彼らをみていると、例外なく、一つの共通項があります。
それは、
『成功した人は、成功する前から、別の成功者が必ずサポートしている』
ということです。
*
これは、簡単でしょうか?
もちろん、簡単ではありません。
成功者が助けてくれるような人は、もちろん成功する確立が高く、そんな人は、もう成功前夜にしてすでに成功者といって過言ではないかもしれません。
これはもう、成功するには、成功する前から成功しろ、という永遠に堂々巡りする成功法則の無限ループみたいなものです。
しかし、これが現実です。
成功は、自分の努力でつかむものではなく、実際は、人がもたらすものなのです。
どれほど、本人が頑張っているか、ということよりも、どれほど、その人を熱心にサポートしてくれる人がいるか、ということが、成功のバロメーターです。
だから、あなたが成功するかどうかは、あなたの周囲の人脈をみれば、すぐわかります。
もし、起業して成功したいと思っていても、今、あなたの周りに起業して成功した人がいなければ、あなたは起業すらできないかもしれません。
反対に、あなたが別に成功したいと思っていなくても、まわりに成功者が集まっていれば、あなたは、勝手に成功してしまいます。
これは、そういうものなのです。
では、こうした「成功するためには、成功している人に助けてもらわなくてはならない。周囲にサポートしてもらわなくてはならない」という前提で、成功法則を考えたとき、
「では、実際、どうやったら、周囲が自分を積極的に助けてくれるようになるのか?」
ということが、究極のポイントとなるわけです。
*
本書、『チャンスがやってくる15の習慣』には、まさにそのポイントがずばり書かれています。
この本を読んで、(ここが大事ですが)ちゃんと実践すれば、あなたの周りの人が、あなたを助けてくれるようになります。しかも、喜んで、自ら積極的に助けてくれるようになります。
成功者は、本質的にこういう成功の実を持っている人が大好きですから、自分からあなたに寄っていくでしょう。
人は、自分に似た人が好きなのです。
「類は友を呼ぶ」というように、成功する人は、成功する人を呼び、成功しない人は、成功しない人を呼ぶものです。
*
さて、いろいろ、おしゃべりが過ぎました。なにしろ、私がこの本を良さを1万時間を尽くして語っても、実際にこの本1冊読む1時間の価値には、遠く及びませんから!
それに、企画を持ち込んできた翻訳者の渋井さんが、この本の原書といかにして出会い、それを実践した結果、彼女はどうなったのか? その物語を知りたくありませんか?
それは、本書で語られる成功のポイントを、体現したような話なのです。
ぜひ、ご一読を! 成功の匂いに敏感な編集者が、究極の一冊として自信をもっておすすめします。
そして、ご一読のあとは、ぜひ、実行を。たった1つでも効果絶大です。
*
この15の習慣は、とても小さな習慣ですが、あなたの生活をよりよくし、より多くの友人を得、成功と幸福を呼びこむ鍵です。
しかし、覚えただけでは価値はありません。
くれぐれも実践です。Good Luck.
※翻訳者紹介
株式会社マチュアライフ研究所 代表取締役社長。
1994年立教大学経済学部経済学科卒業。
都市銀行、専業主婦、百貨店販売、証券会社などキャリア模索を経て28歳のとき起業。
大手企業や金融機関に向けた人材育成、販売コンサルティングなどを手がけるなか、働く20〜30代女性にセグメントしたビジネス人材養成スクールを設立。彼女のセミナーを受講するには半年待ちと言われるほどの人気を集めている。
著書は、累計10万部を超えた『あなたを変える「稼ぎ力」養成講座 決算書読みこなし編』(ダイヤモンド社)をはじめ、『渋井真帆の日経新聞読みこなし隊』(日本経済新聞社)、『仕事心の育て方』(小学館)、『大人のたしなみビジネス理論一夜漬け講座』(宝島社)など、いずれもヒットを記録している。
(編集担当 渡辺考一)
◎――――エッセイ
ストック・オプション会計ですぐに使える計算ソフト
村中健一郎
Muranaka Kenichiro
一九五八年名古屋市生まれ。イリノイ大学理学部数学科卒業、同大学医学・生命科学系大学院修了。カリフォルニア大学ビジネス・スクール等でファイナンスを学ぶ。大手銀行に勤務し、ニューヨークやシカゴでデリバティブ業務を経験。現在、有限会社ケイズソフト代表取締役。著書に『初めてのオプション理論』『技あり一本!! 日経225オプション取引に勝つ』などがある。
企業会計にノーベル賞理論を導入
ストック・オプションとは、役員・従業員があらかじめ決められた価格(行使価格)で自社株を買う権利(コール・オプション)である。例えば、時価500円の株式を行使価格の300円で買い付ければ、200円の行使利益が発生するため、インセンティブ制度として注目されている。このような権利の価値はオプションの価格(プレミアム)に相当する。
2005年12月にストック・オプションに関する会計基準が財務会計基準機構によって出され、2006年5月から付与されるストック・オプションには費用計上が義務となった。企業会計には、(1)認識、(2)測定という二つの大原則があり、費用計上額はプレミアムの公正な評価単価にストック・オプション数を乗じて算定される。公正価値の測定には金融工学が応用されるが、この分野での先駆的な論文の著者は一九九七年にノーベル経済学賞の栄誉に輝いた。
計算ソフトこそ「最強の虎の巻」
会計基準では、少なくとも六つの基礎数値を公正価値測定に考慮すべきだとしている。拙著『ストック・オプション公正価値測定の実務』の付属ソフト「シカゴプロ」(Windows, Excel 97以降で動作)にこの基礎数値を入力すると、公正価値を計算することができる。
例えば、(1)原資産価格(株価の300円)、(2)行使価格(300円)、(3)満期までの期間(6年)、(4)ボラティリティ(43%)、(5)配当利回り(3%)、(6)利子率(2%)という基礎数値を入力すると、どうなるだろうか。
ブラック・ショールズ・モデルによると、96円の公正価値、0.57のデルタ、1.77の価格弾力性となった。このモデルの改良型であるウエイリー・モデルでは、105円の公正価値、0.63のデルタ、1.80の価格弾力性を出力した。
前者のモデルは、権利の行使が満期日においてのみ可能なヨーロピアン形式のオプション取引を前提に開発された。ところが、ストック・オプションは満期までであればいつでも権利行使できるアメリカン形式である。後者のウエイリー・モデルは、アメリカン・オプションに適しているとされる格子モデル(『企業会計』2007年3月)による計算を高い精度と効率で近似する。
デルタとは、第一にヘッジ比率を意味する。原資産の株券一単位に対して、デルタの逆数に相当する数量のコール・オプションを売ればリスクヘッジが可能となり、この状態をデルタ・ニュートラルという。この条件下で値付けされるオプションの価格はフェア(裁定機会の不在によって)となり、これがストック・オプションの公正価値となる。第二に、デルタの絶対値はオプションが権利行使される確率と解釈できる。
価格弾力性は、原資産の価格が一パーセント動くと、プレミアムが何パーセント動くかを示すため、オプションがもたらすレバレッジ(テコの効果)の指標である。
ストック・オプション公正価値測定の難所は、権利の期限前行使だけではない。配当率が利子率(国債の利回りなど)を上回る水準で推移すると、負の持ち越し費用によるブラック・ショールズ・モデルのミスプライスを実務ではたびたび経験する。
基礎数値を少し変えるだけで公正価値は変わるが、その程度については、実際に理論価格を計算してみないとわからない。「シカゴプロ」を使えば、さまざまなケースを想定したシミュレーションができるのである。
ボラティリティはエクセルで簡単に計算できる
基礎数値の一つであるボラティリティは、株価変動の大きさというリスクを表す。それには、ヒストリカル(HV)とインプライド(IV)がある。HVは株価の過去データから統計的手法によって推定され、IVはプレミアムの市場価格からオプションの価格評価モデルを使って計算される。
ストック・オプションには市場取引がないため、HVを使うのが一般的である。しかし、今後の株式オプション市場の成長を見込み、「シカゴプロ」にはウエイリー・モデルを使ってIVを計算する機能も備わっている。
一方、HVの計算には、株価の対数正規分布性など統計学の基礎知識が不可欠となる。付属のCD―ROMには、株価データのエクセルによる計算・分析例が入っている。これを手本にすれば、誰でもHVの計算ができるだろう。また、過去データの量が少ないときに正しい推定値を得るための修正係数のほか、オプション取引の損益計算方法などもエクセルファイルとしてまとめたので、参考になるはずだ。

『ストック・オプション公正価値測定の実務--現場ですぐに使えるストック・オプション計算ソフト付き』
●8400円(税5%)
◎――――連載
美人のもと 第20回
美人のもと
西村ヤスロウ
Nishimura Yasuro
1962年生まれ。株式会社博報堂 プランナー。趣味は人間観察。著書に『Are You Yellow Monkey?』『しぐさの解読 彼女はなぜフグになるのか』など。
*居座り
友人と食事をするのは楽しい。おいしいものを食べながら、いろんな話をする。昨日見たテレビ番組の話でも楽しい。
食べる瞬間というのはとてもストレスから解放され、本能に正直な時間である。たわいない話でも幸せである。
ところがそういうリラックスできる時間でも、心からリラックスすることはまずい場合が多い。人気の店でランチを食べている時などは要注意だ。なにしろ、人気があるからランチタイムは行列ができる。当然、待っている人は早い回転を望んでいる。
しかし、女性のランチは長い。他人のものが出てくるまで手をつけない人が多い。暖かい食事も冷めてしまう。一人で先に食べるのはどうも気まずい。自然に「まだの人」の視線を感じる。しかし、待たれるほうがもっと気まずい。だから、先に食べればいい。出されたものを前にして待っている女性の顔はどうしても美人から離れていく。視線が不自然。自分の前の食事と店内を行ったり来たり。会話しているようで、上の空。キョロキョロさん。これでは美しい目が育たない。
食事も遅めである。早く食べ終わるとまた気まずい。自然と遅くなる。美人は自分のペースで楽しんでいるのに。
問題は食事の後。混んでいる店なら、なるべく早く出るべきである。それなのに、食べ終わっても立たない。食べるものもないのに立たない。飲むものもないのに立たない。食器も下げられているのに立たない。そういうテーブルには美人は少ない。
なぜ、そんなに居座るのか。何も出ないぞ。いや、待っている人から文句が出る。立ち上がろうと誰かが言うまで待っている。自分から言わない。だから待つ。意味なく待つ。会話も尽きたのに待つ。待っているのに、待っていないフリまでする。ここでも上の空のキョロキョロ。
美人は店の空気を自然と感じて、気持ちよく出て行く。もちろんおいしくいただいたので笑顔だ。一方、立たないさんたちはごちそうさまの言葉もなく去っていく。おしかったのか? 実は味に記憶がない。タイミングのことで振り回されているからだ。
おいしいものを食べている瞬間の女性は実に美しい。見ているだけで人を幸せにする。そういう幸せの瞬間はできるだけ多く持つほうがいいに決まっている。
*せんべい
せんべいはうまい。時々食べたくてしかたなくなる。できれば硬いやつ。大きな音が出るほうが好きだ。パリパリだ。
こういう大きな音が出る食べ物は男性的だ。女性は音を立てるのがあまり好きではない。なるべく音を立てないように食べる。
だが、せんべいを食べる女性の姿は美しい。音を立てながら食べている姿は一生懸命に見えて実にかわいい。平べったいものを口に挟み、パフパフしている姿は可愛い動物のようだ。その平べったいものであり、さらに硬いので顔が真剣になる。このひたむきさが素晴らしい。きっとせんべいは「美人のもと」を育てる。
そんな素敵な食べ物を、もったいない食べ方をする人が多い。コナゴナに砕いてから口に入れる人だ。そんなに小さくしなくても。この小さく割っていく時、なぜか眉間にしわをつくり、鼻の穴を膨らませる。どんどん「美人のもと」が減っていく瞬間だ。
しかも、食べていると粉が指につく。それが嫌なので指と指を刷り合わせて、粉を落としていく。その姿は鼻くそを丸めているようだ。妙に慣れた手つきだとがっかりする。
せんべいは割らずに食べよう。思い切って噛みつこう。噛みついている上唇は結構かわいいのだ。
そして重要なのはせんべいを両手で持って食べること。両手で持っている姿はひたむきで美しい。せんべいにしっかり向き合っている。特に最後に小さくなっても両手で持ち続ける姿がたまらなくかわいい。
音が出てもいいのだ。両手で持っている限り、一生懸命に見える。その時、音はその一生懸命さをいい感じで演出してくれる。
さて、今日あたりせんべいを食べてみないか。たまにはパリパリで「美人のもと」を育てるのだ。
◎――――エッセイ
東大入試問題は日本で一番面白い「脳トレ」だ
東大生 入試問題研究チーム
Todaisei nyushi-mondai kenkyu team
現役東大生(執筆時)のみ9名による、東京大学入試問題の解答・解説執筆チーム。所属は医学部、工学部、経済学部、文学部など文・理にわたり様々。それぞれの得意科目では絶対的な自信を持つ一方で、予備校の講義などとは違う独自の「解き方・考え方」を採る個性派集団。
実はとても面白い東大入試問題
「なぜ、『夕焼けは晴れ、朝焼けは雨』なのか」「なぜ、晴れた夜は冷え込むのか」
子ども向けのクイズでも、気象予報士の試験でもありません。2000年に出題された、東大入試の問題です。
東京大学に入るのは難しい、というのは本当でしょうが、その唯一の関門である入試問題については、あまり知られていないのではないでしょうか。特にその「面白さ」の部分は、「ドラゴン桜」にも描かれてはいません。しかし実際のところ、東大入試には面白くてためになる、極端にいえばエンターティメント性の高い問題が少なくないのです。
大人にはいま、「脳トレ」が人気のようです。また電車やバスの中で「ナンクロ」や「数独」をやっている人もよく見かけます。東大入試は、そうした知的トレーニングの要素は十分以上にあるといえるでしょう。「楽しみながら解ける東大入試」という本のコンセプトは、そんなきっかけで思いつきました。
受験生に役立ち、大人も楽しめる
東大入試問題のベスト100を過去20年間の出題から収集し、現役東大生のチームが新たに解答・解説を行う。チームは瞬く間に集合しました。自分がかつて本気で取り組んだ問題を、気楽な立場で再体験したいという思いもありました。しかしなにより、東大生は東大入試のエキスパートでもあります。なにしろ、自分が過去に必死で勉強したことのある過去問なのですから。センター試験とは違って新聞発表などされない東大の入試問題ですが、現役東大生にとっては懐かしく、また記憶に生々しい問題なのです。
しかも、予備校の先生とは全く違った視点で、問題を解説する自信もありました。予備校の講義は、万人に共通の解き方を教えてくれます。しかし実際の東大入試では、現場でとっさに対応しなければならないような問題が少なくないのです。東大入試をくぐり抜けた現役東大生は、そうした「火事場の馬鹿力」的な個性的解答法を身につけています。これをムダにする手はない。
結果として、「大人も楽しめる」けれども、「受験生にも役に立つ」東大入試の本ができることになりました。9名の家庭教師を雇うより、はるかにお買い得なはずです。
9名のチームは、文学部も入れば医学部もいる、文系・理系の混成チームです。得意科目もそれぞれ違います。そのひとりひとりが、得意科目を中心に解答、解説を担当しました。本が出てみてなにより面白いのは、他の人間がどうやって解いているのかが分かったことでしょうか。自分とは、思考の回路が全然違っていたりするのです。これも、一筋縄ではいかない東大入試の奥深さをしめしているのではないでしょうか。
とはいえ、執筆者ひとりひとりが得意分野を担当したことで、解法と解説は、もっともわかりやすいものになっています。「その科目で点が取れたから、東大に入れた」東大生の解き方には、目からウロコです。非常にスマートな数学の解法、無理やりに正しい選択肢をひねり出す文系科目の力技は、同じ東大生でもうなります。現役医学部生による「生物」の解説などは、理科の解説とは思えないほど滑らかです。
東大入試にみる「茶目っ気」
「円周率が3・05より大きいことを証明せよ」
この問題は、2003年の出題です。ちょうど「ゆとり教育」への批判が大きくなっていた頃のことで、この問題は「円周率は3」と教えることになった小学校教育への問題提起、とまで言われました。たしかに東大らしい問題ですが、社会批判というよりは、東大の先生らしい「真面目な茶目っ気」みたいなものを感じます。
ちなみにこの出題は、その年のサービスとまでいわれたほど、簡単な解法がある問題です。解き方は、ぜひ本書をご覧になってください。

『現役東大生がまた解いた東大入試100問』
東大生 入試問題研究チーム:著
●1470円(税5%)
◎――――連載
気になるキーワードを徹底研究
ビジネスマンのための健康ラボ 第20回
【筋トレとダイエット】
竹内有三(医療ジャーナリスト)
メタボリックが気になる中高年サラリーマンの間で、ダイエットのために筋トレに精を出す人が増えてきているようです。会社帰りにジムに寄って、あるいは自宅でダンベルを使って汗を流す。その意気や良し、と言いたいところですが、ひとつ気になることがあります。
もしかしたら、こんなやり方をしていませんか? 筋肉を効率よく鍛えるために、できるだけ重い負荷をかけている。時間が限られているので、屈伸のスピードは速めにしている--。気持ちは分かりますが、実はこれ、筋肉のメカニズムに疎い素人の方が陥りやすい落とし穴。とりわけ、ダイエットに関してはほとんど無駄骨に近いとか。
筋肉は大別して速筋と遅筋とに分けられます。速筋は表層筋ともいって体の表層部にあり、収縮速度が速く、主に跳んだり走ったり、体を速く動かすときに使われます。いわゆる“筋肉ムキムキ”も、もっぱら速筋を鍛えたものです。一方の遅筋(深層筋)は外からは見えない体の深層部にあり、主に姿勢を維持する役目を担っています。速筋のように目立たないので筋トレでも軽視されがちですが、ダイエットをしたいのなら、この遅筋を重点的に鍛えなくてはなりません。
スポーツ科学の第一人者、宮崎義憲・東京学芸大学教授によれば「速筋のエネルギーがブドウ糖であるのに対し、遅筋のエネルギーは脂肪。どちらを刺激したほうがダイエットに有効かは自明の理」ということになります。
この遅筋を鍛えるポイントは「軽い負荷をゆっくり、長くかけること」。前記のように「重い負荷を速く」かけても、脂肪を燃焼させない速筋ばかりを鍛えることになってしまうわけです。ちなみに、宮崎教授は「遅筋を鍛えるならダンベルやマシンは必要ない」として、かわりにつま先立ちをすすめています。三分間、背筋を伸ばして、ゆっくりつま先立ちを繰り返す。これを一日三回つづければ、十分ダイエット効果が出てくるそうです。
●ご意見・ご感想はこちらまで…healthy@diamond.co.jp

◎――――連載
小説「後継者」第36回
第14章 初戦--(1)
安土 敏
Azuchi Satoshi
◆前回までのあらすじ
スーパー・フジシロの創業者社長・藤代浩二郎が、提携先の大手スーパー・プログレスを訪問した帰り、車中で謎の言葉を残し急逝した。その後プログレスは裏切り、フジシロは独自路線を貫くことを決める。しかしフジシロに敵対するかのようにプログレスの子会社アドバンスが出店するという。フジシロはプログレス対策会議を開く。会議室では、今後の具体的な対策が検討された。その直後、花崎取締役が退任するという。アドバンスに移った守田社長とは、家族ぐるみの付き合いがあったようだ。花崎取締役からアドバンスに対抗策が漏れることを懸念し、浩介や間宮取締役は動揺する。しかし重成と詠美は心配要らないという。すでに花崎の退任は想定内であり、花崎取締役からの情報漏えい防止の手は打ってあったからだ。アドバンス開店まであとわずか。フジシロは、浩介は、アドバンス対策を上手くできるのか。
1
アドバンス宮里店は2月中旬に開店した。
その朝は、暖冬が嘘であるかのように寒々としていて、暗い空からいまにも小雨が降り出しそうだった。
商人たちが昔からニッパチと呼んできた2月と8月は、不幸を商う葬儀屋など以外のどんな商売にも不向きで、そのうえ、新卒者が社会に出る直前の2月は、どこでも人手不足になっていて人が集めにくく新規開店を避けるのが普通なのだが、すべての要員をフジシロ頼りにしたせいか、あるいは、社長の守田哲夫に営業感覚が乏しいせいか、アドバンスは2月中旬を開店日に選んだのである。プログレスの店の1階に間借りする上町店に先立って、独立店舗で自分の力を誇示したかったので、敢えて早い開店日を選んだのかもしれない。その当日が最悪の天気になったのだから、どうやら運命の神は初めから守田哲夫を見放したようだ。
やがて降り出した小雨を乗せた北風が強くなってきたので、早朝、暗い空に掲げた3つのアドバルーンも、開店時刻には、屋上に引き降ろされた。通常、スーパーマーケットの新規開店では、店を2重3重に取り巻くほどの行列ができることもあるというのに、数人の女性が、冷雨のなか、店頭で身体を縮めているばかり。さびしいこと、このうえもない。
10時少し前には、関係者らしい人々が店頭に現れて、型どおりテープカットの儀式が行なわれた。司会者がカットに立ち会う5人を紹介したが、中央に守田の姿があり、その隣には、もとゲームセンターだったその施設の所有者がいた。左隣にいる唯一の女性は、地元の消費者代表だと紹介された。
ファンファーレが鳴り、「さあ、お待ちかねの開店です」と叫ぶ司会者の声がむなしく虚空に消えて開店の儀式は終わり、開いた扉から、ようやく十数人にまで増えていた客が、あっという間に店内に消えた。
それでも、時が経つにつれて客が増える。11時ごろには、店内は、ようやく混雑している雰囲気になった。
その人混みに紛れるようにして、そこここに、フジシロの社員たちがいる。会社から背広姿を避けるように指示が出ているから、ジャンパーや厚手のセーター姿である。買物籠を手にして客を装っているが、競合店からの調査だとすぐに分かる。アドバンス側は分かっているが、別に何も言わない。本人たちは、もちろんそれを自覚している。そもそも、元フジシロ社員であるアドバンス社員が多いのだから、双方顔見知りがあちこちで出会うということになる。
調査に出向いた人々は12時前にフジシロに戻り、だれが誘うともなく会議室に集まった。
2
「いや、傑作だったなあ」
口火を切って、いかにも愉快そうに発言したのは、生鮮食品担当取締役の狭山周一である。フジシロの管理者のなかでは例外的に理論派、つまり、理屈が先に立つタイプである。
「野田亭のサバみりん干しや太陽軒のシュウマイが、特別サービス品と称して大々的に売られていたのはおかしかった。それにしても、うまいこと、策に嵌ったなあ」
みりん干しもシュウマイも、フジシロの商品に比べて格段に味が劣ると判断されたものだが、花崎に渡された比較表では、その反対の評価が書かれていた。
「いや、まったく見事にひっかかってくれたものだ」と、店舗担当常務の安井達夫もうれしそうである。ハナタカハナアブという不思議な渾名をつけられたのは、浅黒い長顔にやたらに高い鉤鼻のゆえだが、その鼻が一段と高くなっている。「卵豆腐、二度漬け白菜、カボチャの煮物などなど、軒並みと言っていい。あの卵豆腐を『味に自慢』とわざわざ説明されてその気になって食べたら、二度とアドバンスには行きたくなくなるだろう」
人々から、あれも、これもという例がたくさん挙がった。
「特売もどんぴしゃり、直前を叩きました」と誇らしげに言ったのは、間宮取締役である。「相手が、予想どおりプログレス小型店開店のパターンで来ましたから、品目も価格も、第1弾はすべて我が社のチラシで先手を取りました。先方では、まさか研究された結果だとは気づかずに、元フジシロ社員を通じて、チラシの情報が漏洩したに違いないと疑っていると思います。この調子だと、第2弾、第3弾も、アドバンスは我が社のチラシを後追いするようなチラシになるはずです」
「それにしても、客が少なかった。天候のことを考えに入れても、気の毒だった」
堀越が言った。「うちも、いつもよりは多少少な目だが、すぐ目の前に競合店が開店したとは思えない十分な客の入りだ」
「店内のあちこちで、元フジシロ社員に会うのはいやでしたね」と、総務人事担当の小笠原が顔を顰めた。「向こうもばつが悪そうな顔でしたね」
「そんなこと、私は気にしませんでした」と重成が口を出した。「私は会う人ごとに話を聞いてきました。皆、うちに居たときと同じように話してくれました。いや、なかなか大変みたいですよ。アドバンスには、プログレスから派遣されてきている人たちもいるんだそうで、その人たちと、うちから行った連中とが、まったく意見が合わないのだそうです。『もういやになった。フジシロに戻りたい』なんて言ってる奴もいました」
「本当か」
「プログレスではサービス残業が当たり前なんだそうで、そのへんが我が社から行った連中とぶつかる最大の要因だそうです」
「守田さんも困っているだろうな」
「それが、自信満々だそうです。先代なら敵わないが、芝虫に負けるはずがないと言っているそうです」
久しぶりに芝虫という渾名を聞いたので、一座の人々がどっと湧いた。
「何だ。えらく楽しそうだな」
そう大声で言いながら、部屋に入ってきたのは、当の芝虫、浩介だった。
「あや、まずい」
重成が大まじめな顔に戻ったので、また大きな笑いの渦が起こった。
「どうしたんだ」
「いや、どうもしません。すべて順調だと、皆で喜んでいるところです」
「そうかなあ。そういう感じでもなかった」
芝虫こと浩介は首をかしげた。何となく、自分が話題になっていると感じたようだが、そのことについては、何も言わず「すべて皆さんの思うとおりになった。フジシロの社員たちの優秀性に万歳だ」と言った。しかし、その言葉がちょっと皮肉っぽい響きを持っているように感じたので、会議室のなかは喜ぶよりかえって少し緊張した。そのわけは、浩介が続いて発した言葉で明らかになった。
「特売を全部先打ちする。偽情報を流して、まんまと相手を間違った方向に誘導する。そうしたことも戦いのなかでは許される。ゴルフにだって、そういうことはある。マッチプレーの最終戦、決定的なホールのティーグランドで、さりげなく相手に昔のミスショットを思い出させる一言を呟く。それが相手を安全志向のショットに誘い込む。そして、自分はバーディーを取りにいき、まんまと勝利を奪い取る。そうしたことはあるし、それを非難すべきではない。でも、それは、あくまで互角の勝負の最終段階での、しかもきわめて例外的な話としてのみ価値があるのだ。そんなことを、始終やっていたら効果がなくなるだけでなく、逆に、そういう小手先の偽計が自分の敗因になる。そういうゴマカシの技術で、すべてのホールを勝ち抜くわけにはいかないのだ。基本的に、戦いはあくまで正攻法、力と力、技と技で決着を着ける。どんな戦いも実際にそうだし、そうでなければならない」
会議室のなかにいた20名ほどの男たちが、長く沈黙した。実際にはおそらく1分にも満たなかっただろうが、人々には限りなく長く感じられた。
やがて、「分かりました」とだれかが言った。
「そのとおりだと思います」という声が続いた。
「そうします」「もちろん、正攻法で勝ちます」などという言葉が後を追った。
「正攻法で、アドバンスにも、プログレスにも、絶対に負けません」と、意気込んだのは間宮取締役である。間宮は、花崎退職後のグロサリー担当役員の仕事を兼務しているから、特に責任を感じたのだろう。
「さあ、明日からの作戦を粗漏なくやろう」
その浩介の言葉で、人々は、ほとんど一斉に立ち上がった。浮かれたような雰囲気は一掃されていた。
3
浩介は、自ら指示を出して、宮里地区におけるフジシロ、アドバンス両店の客数を、毎日、午前11時と午後4時の2回、実際に数えさせた。開店初日に、アドバンスを見てきた者たちからの報告が、きわめてばらつくことに気づいたからである。ほとんど同じ時刻にアドバンスの店を見て帰ってきた者たちが、「大したことはなかった」「かなり入っていた」「開店初日だから、我が社より客は多いが、物足りないだろう」「いや、むしろ我が社のほうが入っていた」などと、まちまちなことを言う。そのとき、浩介は、数年前に戦ったゴルフ競技のことを思い出した。
クラブ対抗戦で戸高カントリーの代表のひとりだった浩介は、しぶとい相手との戦いで、最終ホールまでもつれこんでいた。18番はパー4で、浩介と相手とは、ともに第2打を外したが、相手のほうがグリーンの少し手前にあるのに対して、スイートスポットを外れた浩介の第2打はかなり短くて、ピンまで40ヤードあまりを残していた。打ち上げを考えに入れれば48ヤードか。その距離を頭に置いて打とうとした浩介だったが、ふと違うのではないかと感じた。砲台グリーンの奥からの逆光線がピンまでの距離を遠く見せているような気がした。まさに打とうとした瞬間だったから、スイングを止めるのにかなり勇気が要ったが、浩介は敢えて止めた。そして、「すみません」と相手に頭を下げると、ピンまで実際に歩いてみたのである。測った結果は、驚いたことに33ヤード。打ち上げ分を入れて40ヤードだ。今度は確信をもって浩介は打った。サンドウェッジのフェースが正確に捉えた感触を残して、球は思ったとおりの角度に飛び出し、やがて旗竿に当たるカチンという小さな音と歓声が聞こえた。打った本人には見えなかったが、球はホールに吸い込まれたのだ。それが、チーム勝利の瞬間だった。プレーを中断してまで歩測したから得られた結果だった。
「分からなければ、見当でやらずに実測せよ」が、以来、浩介の規範となった。だから、客数も「実測せよ」と言ったのである。調査地点は2カ所。入り口の青果売り場から鮮魚売り場に向かう通路と、レジ回りである。
もちろん、まったく同じ時刻には調べられないが、ほぼ同じ時刻に同じ人に調査させれば、かなり正確と思われる数値が得られる。試してみると、浩介自身が実際に見たものを裏書きしていた。
「素晴らしいですね」と、その話を聞いた詠美が誉めると、「芝虫は、やはりゴルフから得た教訓を活用するに限る」と浩介はニヤリと笑った。
浩介が両店の状況を正確に掴もうとしているということは、フジシロの社員たちにとってうれしいことであった。
「おい、似てきたぞ」と言い出した者がいる。「細かいところ、正確でないとうるさいところ、実際に調べろとすぐに言うところ。先代にそっくりじゃないか」
「そうか、やっぱり親子だなあ」
「もう芝虫なんて呼べない」
冗談めかした笑い声の言葉だったが、言うほうも聞くほうもうれしそうだった。
4
客の入りは、日が経つにつれてフジシロに有利に変化していった。新規開店チラシの対象期間だった最初の3日間とチラシ第2弾の初日の通算4日間は、さすがに60対40でアドバンスが優勢だったが、5日目にはほぼ互角となり、それ以降はフジシロの客数が徐々に伸びていった。アドバンス開店の3週間後には、客数を数えるまでもなく、フジシロの客の入りがよいと分かる状態が続くようになった。
「気を緩めてはならない」
浩介はそう言いながら、本部の営業部隊を回ったのだが、もう勝負は明らかになっていて、浩介が檄を飛ばしても、どこか白ける感じでさえある。
「もう宮里店のことは忘れて、フジシロ中央店対プログレス上町店の対策に力を入れるべきです」と、佐藤詠美はアドバンス宮里店開店の直後から言っていたのだが、まさにそのとおりになった。
「中央店勝利の鍵はジャストインタイムの売り場づくりです。そのためには、常に必要な人員が確保される体制を作る必要があります」
詠美によれば、ジャストインタイムの売り場づくりとは、営業時間中常に生鮮食品売り場に必要に応じて、出来たての新鮮な商品が供給され続けるということである。
スーパーマーケットには、客がひっきりなしに入ってきて、肉・魚・野菜・総菜などの生鮮食品を売り場から取り、自分の買物籠に入れていく。よく売れる商品は、たちまちのうちに品薄になる。その状態をチェックして、『次にどんな商品を作り補充するか』を考えているのが、肉・魚・野菜・総菜などの各商品部門にいるチーフと呼ばれる責任者である。彼らは、商品が品切れする前に、売り場の後方にある生鮮食品作業場に指示して、補充すべき商品を作らせる。その『売り場チェック→作業指示→商品づくり・補充』が適切かつ順調に行なわれればジャストインタイムになる。理屈はそのとおりだが、なかなかそうならないのは、『売り場チェック→作業指示』はできても、実際に作業をさせることがなかなかむずかしいのである。
当たり前のことだが、作業をさせるためには、作業員が必要数だけ存在することが絶対の条件だ。だから、いつ何時発生するか分からない作業に備えて、常に必要人員を確保しておけばいいのであるが、そんなことをしたら、ものすごい人員のムダ、つまり人件費のムダが発生する。かと言って、人員を絞れば必要なときに作業員がいないおそれがある。少し妥協して、売れそうな商品を作り溜めしておくという手はあるが、それでは出来たての商品ではない。
「ジャストインタイムの仕組みは、営業時間中に商品が売れた結果として発生する、新たな製造必要パック数を正確に予測して、作業が必要になるまさにそのときに、その作業にぴったり合う作業員数が待機していることによって可能になります」と詠美は言うのである。
「それは大変なことだ。そんなことができるだろうか」
浩介は首を捻った。
「できます。チャレンジしましょう」
詠美は、断言した。
◎――――連載
連載エッセイ ハードヘッド&ソフトハート 第64回
大学院重点化の不思議
佐和隆光
Sawa Takamitsu
1942年生まれ。立命館大学政策科学研究科教授および京都大学経済研究所特任教授。専攻は計量経済学、環境経済学。著書に『市場主義の終焉』等。
矛盾する二つの大学改革
一九九〇年代に入り、旧文部省は「大学院重点化」という方針を打ち出した。大学の教育研究組織を、従来の学部を基礎とした組織から、大学院を中心とする組織に変更することが、その意味するところである。
一九九一年四月、最も早く「重点化」されたのは、東京大学法学部であった。東京大学法学部では、法曹界や官界に優秀な人材が流出するのを防ぐために、成績優秀者を大学卒業後すぐに助手に採用し、三年後に助教授に昇進させるという人事システムを採用していた。法学部は、他学部と比べて、相対的に、大学院教育にさほどの重きを置いていない、と常日ごろ感じていた私は、法学部が大学院重点化の先駆けとなったことに驚いた。
私が想像するに、国際公務員、すなわち国連などの職員になるためには、修士号の学位取得が必要条件の一つとされていたことが、大学院重点化が法学部から始まった理由のひとつであろう。ともあれ、九二年度から九八年度にかけて、旧帝国大学の学部が順次、大学院重点化された。
大学院重点化によって、何がどう変わったのかというと、大学院の定員が大幅増となったことである。また、国立大学の先生の名刺の肩書が、○○学部教授から○○学研究科教授に変わったことは、読者の皆様方もご存知のとおりである。だからといって、給与や待遇面で何かが変わったわけではいささかたりともない。
ほぼ同じころ、学部の教養課程の教育に関する規制が緩和され、教養課程での科目履修に関しては、各大学・学部の自主性に委ねられることとなった。その結果、教養科目の必須単位数は減らされ、大学一年生から専門科目の単位を取ることが許されるようになった。
大学院重点化という施策と教養課程の規制緩和は、相互に矛盾する施策ではなかったろうか。なぜなら学部在学中の四年間かけて専門科目を学び、さらに大学院でも、というのは屋上屋を架すに等しいからである。大学院を重点化し、大学院への進学率を上げるのなら、学部学生には、より高度な教養教育を授けるべきである、と考えるのは私のみではあるまい。それはさておき、大学院重点化の結果、いったい何が起きたのだろうか。
大学院の大衆化が研究者養成を阻害する
第一に、大学院の「大衆化」である。重点化されるまでは、文系の研究科に進学を希望するものの全員が、学者になることを目指していた。文系の大学院で修士の学位を取得しても、民間企業への就職の道は閉ざされていたし、官庁もまた法学や経済学の修士号をまったく評価しなかった。そのため、大学院に進学する者のほとんど全員が博士課程に進学していた。博士課程の定員は、修士課程の定員の半数とされていたため、修士課程修了者の全員を博士課程に進学させるために、修士課程には定員の半数以下しか入学させなかった。
こうしたわけで、大学院に進学する学生のモチベーションはきわめて高く、入学早々から、かなりレベルの高い専門書を輪読することができた。私の経験からいうと、大学院一年生のとき、経済学の関係ではポール・A・サムエルソンの『経済分析の基礎』を輪読した。その他、統計学の関連では、きわめてハイレベルのテキストを輪読あるいは自習した。ところが、大学院の大衆化のおかげで、大学院の新入生には、マクロ・ミクロ経済学の基礎を手取り足取り教えなければならなくなり、いまや授業のレベルの低下ぶりは目を覆いたくなるばかりである。
大学院の修士(博士前期)課程の学生定員が大幅に増え、しかも、定員を充足することが必須とされるようになったため、また二股、三股の受験が可能となったため、毎年二月ごろに二次試験を実施しない限り、学生定員を満たせなくなった。その結果、大学の学部教育で経済学を専門としなかった学生が、経済学の入門的教科書で受験勉強を数ヶ月かけてやり、理系の学生ならば、数学と英語で点数を稼げば、難なく入試に合格できるようになった。こうした学生が多いからこそ、マクロ・ミクロ経済学の基礎を学ぶ機会を提供する必要が生じてしまったのである。
経済学の修士号取得者の人数を増やし、エコノミストの「職業化」に多少とも貢献するという意味で、大学院の大衆化が、それなりの社会的意義をもったのは事実である。しかし、学者を志す学生にとっては大の迷惑である。なぜなら、マクロ・ミクロ経済学のABCは、すでに勉強ずみであり、もっとハイレベルなテキストでの授業を望んで大学院に進学したにもかかわらず、こんな易しい授業をされたのでは堪らないからである。そんなわけで、大学院重点化に伴う大学院の大衆化は、高度な研究者ないし学者を養成するという観点からは、大いなるネガティブ効果をもたらしたのである。
念のため断っておくが、工学部では、事情はいささかならず異なっていた。一九六〇年代から、修士号の取得が就職面で有利に働くようになったため、ほぼ全員が大学院への進学を志し、その入試倍率はかなり高かった。ただし、博士号の取得までは会社側の求めるところではなかったため、博士課程に進学する(将来、学者を志す)学生は、ごく少人数しかいなかった。
工学研究科においても、大学院重点化により学生定員が大幅に増えたため、入試のバリアは低くなり、学生の「質」が著しく低下したそうである。こうした学生の質の低下は、ほとんどあらゆる分野で進んでおり、旧文部省による大学院重点化という施策の悪影響の大きさは計り知れない。
大学院の大衆化のおかげで、文系の大学院で修士号を取得した学生に、民間企業への就職の門戸は開かれた。しかし、私の知る会社の人事担当者の言葉によれば、平均して言えば、同じ大学の学部在学生のほうが、修士課程在学生よりも入社試験の成績は優秀だそうである。しかも、経済学や法学の修士号を人事考査の上で評価する会社は少ないのが実情である。
専門職大学院の不思議
文部科学省が次に打ち出したのが専門職大学院の設置である。まず手はじめに、法学部を有する、ほぼすべての大学に法科大学院(ロースクール)を設置し、ゆくゆくは司法試験の受験資格を法科大学院卒業見込み者に限ることとした。しかも、司法試験の合格者の人数を約五倍増とした。さらに、ビジネススクール、公共政策大学院(公務員養成が目的)、会計学大学院など、次々と専門職大学院を新設した。会計学大学院は、公認会計士という専門職があるから、専門職大学院というにふさわしい。経営学修士(MBA)の学位が日本では評価されないため、ビジネススクールは専門職大学院というにふさわしくない。
公務員の養成を目的として設置された公共政策大学院では、学生のほとんどが一年生のときに公務員試験を受験し、合格して念願の官庁への就職が決まれば、ほぼ確実に中途退学するから、その存在意義が問われねばなるまい。本来ならば、公共政策大学院の開設に伴い、修士号取得予定者を対象とする(最上級)公務員試験を新設し、その合格者から採用されたものが最高のエリート官僚とみなされるような人事システムが確立されていなければなるまい。
研究者市場における「セイの法則」
こうした一連の改革のモデルとなっているのは、アメリカの教育制度である。教育制度の改革を実施するに当たっては「制度の補完性」ということが配慮されなくてはならない。教育制度の改革を考えるに当たっては、初等中等教育、大学教育、大学院教育、社会の受け入れ体制のすべてに、整合的な改革を施さねばならない。大学院だけを改革したのは「制度の補完性」をわきまえない改悪だったといわざるを得ない。
アメリカの大学の学部(アンダー・グラデュエイト)では日本の高校レベルの教育が施される。大学四年間、アメリカの大学生は、日本の高校生並みに勉強する。一八歳の大学新入生には、たとえば、主専攻が数学、副専攻がジャズ音楽といった具合に、自分の適性を探り当てる試行錯誤の機会が与えられる。自分は数学が得意だと思って主専攻を数学にしたのだが、高度な数学にはついていけず、限界を知った学生は、主専攻を生物学や経済学に変更する。将来の職業に直結する教育を施す場が大学院(グラデュエイト・スクール)なのである。わかりやすい例を引くと、アメリカの医師や弁護士を養成するのは、メディカル・スクール、ロー・スクールといった専門職大学院なのである。言い換えれば、学部レベルでの医学部や法学部は、アメリカの大学には存在しない。
以上述べ来たったとおり、大学の学部教育のあり方が、日米間で根本的に異なっていることを看過して、大学院重点化、専門職大学院の創設という措置を講じたことは、害あって益なしだと私は考える。繰り返しになるが、大学院を重点化するのなら、同時に、学部教育をリベラル・アーツ・アンド・サイエンス(一般教養的科目を幅広く)に塗り替えるべきである。さもないと、日本の若者の無教養はさらに加速することになる。
ここで詳述する余裕はないが、後期博士課程修了者(ポストドクター)の数を増やすという「ポスドク一万人支援計画」といった国の計画も、ポスドク研究員が任期制のため、数多くの三五歳を過ぎた博士たちを路頭に迷わせかねない。「供給がそれ自らの需要を創り出す」という「セイの法則」は、市場経済におけると同じく、研究者市場においても成り立ち得ないのである。
◎――――連載
瞬間の贅沢23
武田双雲
Takeda Souun
1975年熊本県生まれ。書道家。http://www.souun.net/
5年間に書きためた書と詩が一冊になりました。『たのしか』好評発売中(詩には英・中国語訳つき)
「間」
近すぎたら 傷つけ合い、
遠すぎたら 届かない。

◎――――編集後記
編集室より………
先日、大手企業の元社長の奥さんと食事をした。元社長は昨年亡くなっており、奥さんを激励しようと誘った。元社長はちょっとした不祥事で十年ほど前に退任したが、部下たちは辞めた原因が原因なのでごく親しかった者を除いてほとんど寄り付かなかった。奥さんは「世の中って、そんなものなんでしょうねえ」と淋しそうに語っていた。
元社長は病気のため六、七年前から手足が不自由だったが、動かないと病が重くなると奥さんがせっせと外に連れ歩いていた。そんな奥さんの努力の甲斐もなく、二年ほど前からは寝たきりになってしまった。奥さんの懸命の看護が続いた。
夜中、一時間おきに起きて世話をしなくてはならない。大きな病院に入院したあとも、奥さんは看護婦まかせにせず、すべて毎日一人で看護した。
どんなに親しい肉親でも、介護が続けば疲れていやになってしまう。世の中では介護に疲れての殺人などのニュースも後を絶たない。でもこの奥さんは「ちっとも苦にならなかった」という。「それだけ愛していた」とも。だから肉親が「介護を代わるから、気晴らしでもしてきたら」と言ってくれても、とてもそんな気にはならなかったそうだ。
それだけやったのに、いま振り返ると、「もっとできたことがあったのでは」とか「ほんとうにあんな看護でよかったのだろうか」と思うそうだ。
結局、元社長は昨年、静かに息をひきとった。亡くなった直後は気が張っていたのでそうでもなかったが、四十九日を過ぎたあたりから急に淋しさがこみ上げてきたそうだ。奥さんは今、元社長が元気だったころの二人の写真を大事に持ち歩いている。「本当に好きだったのよ」と。晩年、仕事の面では幸せとはいえなかった元社長だが、この奥さんと一緒に静かに過ごせて、本当に幸せだったことだろう。(湯谷)
お知らせ………
▼こころのクオリティ・オブ・ライフマガジン「ジッポウ」新創刊のお知らせです。ジッポウとは「十方」。地上の八方向に上方・下方を加えた全方位を意味します。現実世界(八方)ばかりを気にしてきた人たちにあの世とこの世という関係を意識してもらいという願いが込められています。読者ターゲットは団塊の世代。「こころの問題=生きるというのはどういうことなのか」を、「生・老・病・死の問題」として捉え、一流の執筆陣を通じて問題提起し、解決していく人生誌です。
「経済、経営、株・マネー」といったいかにも現実的なテーマでの刊行物が中心の小社にとっては、「こころのサポート」は今までにない新たな挑戦です。是非、ご一読いただければ幸いです。「ジッポウ」(定価1500円・年4回発行)は4月9日(月)発売予定。(※一部地域により異なる場合がございます)(岩佐)
「Kei」について
「Kei」はダイヤモンド社の広報誌として全国主要書店でお配りしている小冊子「Kei」の電子版です。論文の投稿を歓迎します
「Kei」では、経済・経営に関する論文の投稿を受け付けております。字数は1000〜4000字。受け付けは電子メールのみです。冒頭に概要、氏名、略歴、住所、電話番号、電子メール・アドレスを添えてください。採否についてのお問い合わせには応じられません。採用の場合は編集室より電子メールでご連絡します。受け付けのアドレスは以下のとおり。
kei@diamond.co.jp
発行人 湯谷昇羊
編集人 田上雄司
発行所 ダイヤモンド社
住所 〒150-8409 東京都渋谷区神宮前6-12-17
(電話)03-5778-7241(マーケティング局)
ダイヤモンド社のホームページ
http://www.diamond.co.jp/
ダイヤモンド社 2007
本誌記事の無断転載・複写を禁じます。